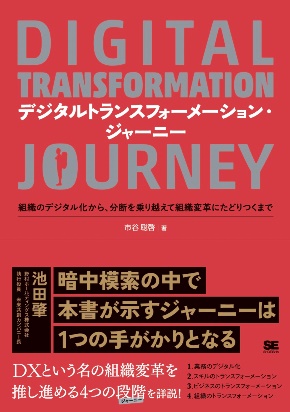第1回 「荒ぶるDX四天王」に立ち向かうすべを備えているか:“デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー”ではじめるDX2周目(1/2 ページ)
DXの取り組みに正解となる「道筋」があらかじめあるわけではない。あくまで自組織の現在の立ち位置(From)を踏まえて、どこに向かっていくか(To)を自ら定め、そのFromからToに至るためのギャップを乗り越えていく活動となる。
DXに模範解答となる「正解」は存在するか?
日本中の企業組織が、デジタルトランスフォーメーション(DX)への意識を高めていると言っても過言ではない。筆者は、大企業から中小企業、地方企業まで広く組織運営や事業創出の支援に携わっている。この数年のうちに、企業のDXのへの感度は極めて高まっているというのが実感としてある。
ただ、実際には経産省のDXレポートやIPAのDX白書が示す通り、日本企業のDXが大きく進展しているわけではない。冒頭でも「意識は高まっている」とは述べたが、実行・実践が進み、なおかつ成果があがっているという段階に至るにはまだ遠い。
筆者はこれまで数十社のDX支援を手掛けており、そこで得られた知見を書籍「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー」にてまとめている。この連載では、書籍の要点をピックアップしながら、DXの本質へと迫りたい。今現在からDXをはじめる、あるいはDXの取り組みを見直し、やり直すことを講じたいという人はぜひ読んでほしい。
最初に言っておくと、DXの取り組みに正解となる「道筋」があらかじめあるわけではない。あくまで自組織の現在の立ち位置(From)を踏まえて、どこに向かっていくか(To)を自ら定め、そのFromからToに至るためのギャップを乗り越えていく活動となる。企業の立ち位置がその数と同じくらいあることを思えば、誰にでも通用する「正解」があるはずもない。
一方、DXでRPAからIOT、データ基盤、AIまでデジタル技術やツールを導入することを想定するならば、先行する事例などは模範解答となりえるのではないかと思う人もいるかもしれない。手段レベルの話であれば確かに事例は参考になる。ただし、DXとは「業務でデジタルを活用してその利便性を高めよう」という単なる手段活用にとどまる活動ではない。
DXの狙いとは、自組織が顧客や社会に向けて提供する製品、サービス、ビジネスモデル自体を再定義し、「これまで提供できていなかった顧客体験」を実現するところにある。あくまで、デジタル技術やデータは顧客に向けた新たな体験(価値)の創出のために利用する。DXの進み具合を見る1つの観点は、ツールの導入状況ではなく、どれだけ新たな価値を生み出せたかである。
なおかつ、こうした取り組みを一過性ではなくて、社会のニーズに応え続けられるよう持続的に行う必要がある。コロナ禍が収束したところで、また業務をアナログな姿へ戻すことは考えられまい。デジタルに順応した社会や環境に向けて、不可逆的にかつ持続的に組織活動のほうを適応していかなければならない。組織から外に向けての提供価値を磨くとともに、それを継続的な活動とする組織体制、運営・運用、制度や仕組みなど組織内部の見直しが同時に求められる。外部へ向けてと内部の変革。DXとはまさしく組織変革に他ならない。
DXで直面する4つの炎上状態「荒ぶるDX四天王」
ゆえに、DXの取り組みは難しい。気が付けば、思ってもいなかった不本意な状況に陥っていることもある。
ここでは、DXでよくある4つの炎上状態を示したい。1つ目は「びょうぶのトラDX」である。びょうぶのトラといえば、寓話の「一休さん」で登場する話である。絵に書いただけのトラをどうこうしようとしてもムダである、やろうとしていることが矛盾していないかを考えようというあの話である。
DXを進める上で、戦略レベル、計画レベルで「びょうぶのトラ」が垣間見えることがある。多大な時間を費やして、分厚いプレゼンテーション資料は完成したものの、いざ実行しようとしても、どのような体制や取り組めばよいか分からない。そうした状況で無理にプロジェクトを始めたとしても丸腰に近く、まずうまくいかない。ときにはひどい炎上へと発展する。
2つ目は「裸の王様DX」。まがりなりにもDXのプロジェクトが走り出し、いよいよ我が社もDXが進められたかとマネジメント層や経営層は一定の満足を得る。ところが、その進み具合はあくまで自組織の中であって、外とはまだまだ比べるところまでいっていない、といった状況がある。そうした層の自己認識を現場は冷ややかに見ていたりする。そのギャップを経営、マネジメントにフィードバックする機会もないため、認識差異がうまることはない。やがて、両者の温度感は決定的となり、3つ目の炎上を迎える。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.