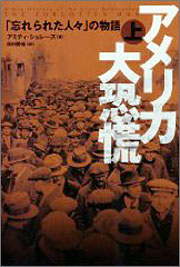知られざる素顔に迫る――「アメリカ大恐慌」:経営のヒントになる1冊
ローズヴェルト大統領のニューディール政策を激しく批判する米国のある女性ジャーナリスト。その背景にある理由とは。世界恐慌の素顔に迫る。
昨年秋のリーマン・ショック以来、世界恐慌への関心は高まるばかりである。米国では1929年に始まった「大恐慌(Great Depression)」に関する書籍は、頻繁に刊行され、研究も充実している。かたや日本においては、数年に1冊出るかどうかで、研究の最先端も一般の人にはほとんど知られていない。
こうした空白を埋めてくれるのが本書といえよう。「The Wall Street Journal」や「The Financial Times」などに寄稿が多い女性コラムニスト、アミティ・シュレーズが大恐慌の膨大な資料にあたり、さまざまなエピソードを挙げてアメリカ大恐慌の大パノラマをつくり上げた。米国では刊行から半年で10刷を超えるベストセラーとなった。
本書の中心ともいえるのが、ローズヴェルト大統領のニューディール政策に対する激しい批判である。今日ではニューディール政策が民間企業の働きを抑制し、大恐慌からの回復を遅らせたという歴史的評価は完全に一般化している。恐慌を本当に終わらせたのは第2次世界大戦による戦争需要だった。
1933年に大統領に就任したローズヴェルトは、TVA(テネシー川流域開発公社)をはじめとする大規模な公共事業政策を推し進めた。不況対策として有効とされたこのような政策について、経済学的というより、一般の人々にもたらした影響をシュレーズは丹念に描いている。例えば、ニューディールの柱の一つだったNRA(全国復興庁)が中小企業に厳しい規制をかけたため、数々の激しい訴訟による抵抗にあったというエピソードが紹介されている(ブルックリンで養鶏場を営んでいたシェクター一家のケース[下巻])。
ローズヴェルトは最初の大統領選の際に、「経済的ピラミッドの最下層にいる忘れられた人々(forgotten man)のために働く」とスピーチしたが、逆に彼のニューディール政策のために犠牲になった企業人や市井の人々が数多くいた。本書ではその人々にスポットライトを当てている。
本書は、これまで日本でほとんど紹介されてこなかった、アメリカ大恐慌の「素顔」が描き出されている。それは決して単に過去のものになったわけではないのだ。下巻には、アメリカ大恐慌研究の第一人者である秋元英一氏の解説も収録。
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 石黒不二代のニュースの本質:【第1回】投資銀行破たんから学ぶ2009年の経営
石黒不二代のニュースの本質:【第1回】投資銀行破たんから学ぶ2009年の経営
米金融崩壊に端を発した経済危機は欧州や新興国をも飲み込み、世界を不況のどん底へと陥れた。目下、経営者は厳しいかじ取りを迫られているわけだが、企業を正しい方向へ導くためには、今起きている出来事の「本質」を理解することが不可欠だ。新連載「石黒不二代のニュースの本質」では、ネットイヤーグループ代表取締役社長兼CEOの石黒不二代氏が米国へのMBA留学経験などを踏まえて鋭い視点で時事問題を斬る。 【新春特別企画】コミュニティーリーダーが占う、2009年大予測:2009年は“真っ暗闇”
【新春特別企画】コミュニティーリーダーが占う、2009年大予測:2009年は“真っ暗闇”
昨年9月半ばの「リーマンショック」以降、深刻な経済危機が世界中を襲っている。その勢いは2009年に入ってからも止まらない。経済のけん引役として期待される新興国も厳しい状況だ。果たしてこの暗闇から抜け出せるのだろうか。 ミドルが経営を変える:【新春特別寄稿】本当にこれから「世界の崩壊」が始まるのか?
ミドルが経営を変える:【新春特別寄稿】本当にこれから「世界の崩壊」が始まるのか?
世界を揺るがす経済危機によって、2009年はより厳しい1年になることが予想される。各方面からは先行き不安の声が絶えない。しかし、実はそれほど悲観するには至らないと考える。 経営のヒントになる1冊:100年に1度の危機は本当か――「大暴落1929」
経営のヒントになる1冊:100年に1度の危機は本当か――「大暴落1929」
初版の発行から50年以上も経つ本書は、世の中が不況や景気悪化になると、きまって売れ行きが伸びるという。今回の経済危機においても同様で、麻生首相も1冊購入したそうだ。