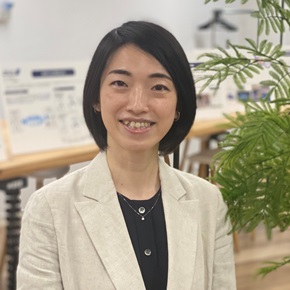ANAがヒアラブル端末を空港スタッフに導入、期待を超える体験を模索(2/2 ページ)
コロナ禍で業績悪化に苦しむ航空業界だが、ANAではむしろDX推進のアクセルを踏み込んでいる。新しい成功モデルを模索する中、DXの取り組みが同社の体質を強くしているからだという。その一例が、空港スタッフへのヒアラブル端末の展開だ。
これまでIT部門の担当ではなかった無線機だったが、現場の課題に向き合う中、ヒアラブル端末への移行推進は自然な流れだった。2020年2月にはPoCを終え、課題の洗い出しを行った。タブレットの展開が落ち着いた今年7月、千歳空港、名古屋空港、伊丹空港、関西国際空港 、福岡空港を皮切りに、9月には羽田空港でも本番展開が始まっている。
ヒアラブル端末導入後は、ハンズフリーで会話ができるようになっただけでなく、音声ファイルとしてクラウドにグループ単位で保存されるため、簡単に聞き直しできるほか、音声データから文字起こしされたテキストもアプリから参照できるようになった。無線機がなくなったことで、その管理という現場での厄介な仕事がなくなったのはもちろんのこと、大幅なコスト削減が図られたことは言うまでもない。
蓄積された会話データが「宝の山」に
今回のプロジェクトを統括するANAデジタル変革室 イノベーション推進部 業務イノベーションチーム マネジャの渡部由紀子氏は、2004年の入社から約10年間、羽田空港の旅客部門で働いたのち、IT部門にあたる業務プロセス改革室(現・デジタル変革室)に異動し、社内ポータルの整備やGoogle Chat、Google Meetなどの導入を進めた経験を持つ。
「わたしたちの強みは現場を知っていること。BONX Gripとアプリの機能が空港業務にフィットするのか、しっかりと見極めることができた」と渡部氏。空港部門と連携し、斜め掛けできるiPadケースを併せて展開するなど、細かな工夫も忘れていない。
ANAでは、現場を経て業務をよく理解している渡部氏のようなIT人材の育成に力を注いでいる。現場を知る渡部氏にとっては、ヒアラブル端末の導入はコミュニケーションの円滑化で終わりではない。無線機とは違って物理的に離れた空港で働くスタッフや整備士をグループ化できたり、チャットボットを導入することでマニュアルやスケジュールを参照したり、バックエンドのシステムに問い合わせもできるようになるはずだ。
さらにクラウドに蓄積された音声データは「宝の山」ともいえる。テキストマイニングで解析することで、潜在的な課題や顧客の不安なども見えてくるはずだ。現場から得られたデータが新たな業務デザインの起点になるという好循環が生まれつつある。
「ビジネスで利用されるお客さまに頼ってきたこれまでの成功モデルは見直しを迫られていて、それに代わる新しいモデルを模索しなければならない。個人でご利用のお客さまやファミリー層を拡大していこうとする中、お客さまが望むものは何か? IT部門もシステムを開発して終わりではなく、デジタルテクノロジーによって生み出されるデータの活用にまで仕事の領域を広げ、可視化された現場の業務から、期待を超える顧客体験とは何かを日々学んでいる」と野村氏は話す。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.