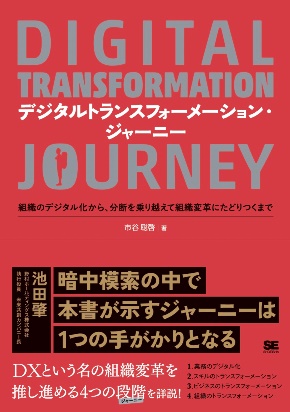第4回 既存事業か新規事業かではなく、既存も新規も進めてこそのビジネスDX:“デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー”ではじめるDX2周目(1/2 ページ)
DXにおいて新たな顧客体験を生み出していくためには、あらかじめ分かりやすい正解などなく、仮説による実験、試行を繰り返しながら進めていくよりほかない。
あらゆる事業で再定義が必要となっている
組織の形態進化を段階的に進める「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー」、前回は「構想と実現のボレー」が不可欠であり、デジタル人材には「仮説検証」と「アジャイル」のスキルセットが期待されると述べた。
DXにおいて新たな顧客体験を生み出していくためには、あらかじめ分かりやすい正解などなく、仮説による実験、試行を繰り返しながら進めていくよりほかない。また、仮説検証のためのプロトタイプや、MVP(Minimum Viable Product)という最小限の範囲のプロダクトを作るのに求められるのは従来の重厚な開発プロセスではない。作り進めていくことで得られる発見や理解、フィードバックに基づき、プロダクトをより適したものへと変える。そうしたアジャイルなプロセスが前提となる。
という話をすると、言わんとするところは分かるが自分のところには関係ないという声を聞くことがある。自分たちが手掛けている事業は、仮説検証やアジャイルなど必要ない。もうとっくにビジネスモデルが確立しており、オペレーションも効率性に最適化している。新たな発見や理解などそうそう生まれない。だから、仮説検証やアジャイルなどまどろっこしい概念は不要なのだという。
こうした考えは、コロナ禍以降あらため直したほうがよい。コロナがもたらした環境変化とは業務オペレーションのデジタル移行だというのは自明だが、単に効率性を高めるとは別の意味がある。既存の事業であっても不確実性が高まっているのだ。これまでリアルで提供してきたサービスをオンラインに移行するということは、それを提供するための業務としてどうあるべきかが問い直されることになる。例えばリアルでの接客が中心だったサービスから、オンライン上での接客、ライブコマースをも手掛けることにしたら、早速、業務の設計と業務体制の適応が求められる。
リアルを中心において磨いてきた業務をオンラインに移した際に、何が正解なのかをするすると導き出せるだろうか。おそらく業務が回るかどうか試行するだろうし、オンライン中心に移行してサービス品質が落ちたということにならないよう探求とそこからの適応をはじめるはずだ。こうした観点で、実は多くの組織が業務の再定義のために仮説検証やアジャイルに取り組むべき状況にあるといえるのだ。既存事業だからこれまで通りで良い、という状況ではない。
デジタルによってありたい姿を引き上げる
オンライン中心に業務を移行した場合に生じるであろう数々の課題。これらは事業の効率を下げる新たな阻害要因なのだろうか。決してそうではない。課題とは、ありたいと描く姿と現状との差分から生まれるものである。逆に言うと、これまでにない新たな課題があるということは、ありたい姿を見つけられているのだ。
もちろん、コロナ禍によるオンラインへの唐突な移行がありたいことだったのかというとそうではないだろう。ただ、デジタル化を進めるために新たな技術の活用に踏み出したことで、結果としてケイパビリティを高めることとなった。コロナ禍は強制的な出来事で望むものではなかったが、これまでの延長線では描けなかった事業の姿を捉え直すエポックでもあったといえる。新たな事業の姿のために必要なITやプロセスが求められ、組織的な適応へと踏み出す機会になった。
事業が社会や取り巻く環境にあわせて進化していくためには、ありたい姿を自ら捉え直すことが求められる。そこでデジタルやデータの活用を講じるのはその促しとなりえる。これまで出来なかったこと、効率性に見合わなかった行為や考え方、こうしたことが乗り越えられるとなるとありたい姿を描き直し、より高いレベルへと移る現実感が得られる。例えばオンライン接客でサービスやモノを顧客に売れる、提供できるとなれば「店舗や窓口に来店できる人が顧客」「リアルに相対できる相手が顧客」という定義を取っ払うこともできる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
ITmedia エグゼクティブのご案内
「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。
入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。
ぜひこの機会にお申し込みください。
入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。
【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上
アクセストップ10
- 専門学校教員からNECのCISOに! 「人生は筋トレ」、訓練は超難題 - NEC 淵上氏
- WBC連覇へ「パワプロ」が侍ジャパン支援 ピッチコム対策でコナミが後押し
- ネトフリ視聴の福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」契約大幅増 WBC効果か
- 情シスから営業へ、異色のキャリアが生んだ「売り込まない」アドバイザー営業 - HENNGE 谷元氏
- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進
- 「Dr.コトー」存続の切り札はドローン 病院から離島へ十数分のフライトで医薬品を輸送
- 「再雇用でいいですか?」元ビルボードジャパンCEOが語る、定年後に稼げる人の準備術
- 中央線グリーン車、収入目標突破へ JR東日本が3月運賃改定 喜勢社長「サービス向上」
- これからはAIとビジネスアナリシスの時代
- 未来の災害を可視化 都市の立体データサービス「プラトー」、自治体で防災活用広がる
アドバイザリーボード
早稲田大学商学学術院教授
根来龍之
早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授
小尾敏夫
株式会社CEAFOM 代表取締役社長
郡山史郎
株式会社プロシード 代表取締役
西野弘
明治学院大学 経済学部准教授