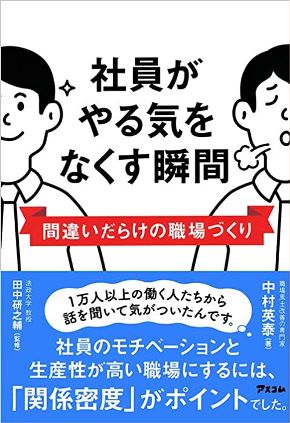「この会社、もうダメだ」……社員のやる気をなくす職場の決定的な特徴(1/2 ページ)
給与の問題、ハラスメントなど明確な理由もなく、社員がやる気をなくす、退社をする。そんなときは、社員同士の関係性、職場の雰囲気、風土が原因の場合がある。では、どうすればよいのか。
給与の問題、ハラスメントなど、思い当たる明確な理由もなく、社員がやる気をなくしたり、退社をしたり。「え? なんで?」と思うようなとき、社員同士の関係性、職場の雰囲気、風土が原因の場合があります。では、どうすればよいのか。職場風土改善の専門家、中村英泰さんが上梓した『社員がやる気をなくす瞬間 間違いだらけの職場づくり』を一部抜粋してお話します。
社員のやる気は職場風土で削られる
“入社したときはやる気がみなぎっていた人が、やる気をなくしていく”。私は、いろいろな職場を見てきて、その原因の多くに、「職場風土」が関わっていると感じています。職場風土は、部署やチームの社員同士の長年の関係性によってつくられる、ある種の文化です。
例えば、活発に意見交換ができる職場なら、社員が互いに相談や連絡をかけあう声で、活気づいた職場風土になります。ワンマンな上司がいる職場では、社員が上司の様子や機嫌をうかがったりする職場風土となります。
また、一切自分の仕事以外のことは考えない人ばかりだと、交わされる話は形式ばった、事務的なものに限られ、お互いにドライでどこか冷めた職場風土となります。叱責が職場に響きわたれば、どんな職場風土になるか想像しやすいと思いますし、ドライでどこか冷めた職場風土でやる気を維持する難しさも、理解できるのではないでしょうか。
人のやる気を決める2つのポイント
人のやる気=モチベーションを出すための要因を、心理学においては動機付けといい、「外発的動機付け」(物的側面)と「内発的動機付け」(人的側面)の2種類があります。
外発的動機付けは、仕事において、企業側が設定した職位や報酬を得ようとして、わき上がるものです。外発的動機付けの代表格である昇格や報酬、希望する部署・地域への異動などの物理的報酬は、企業の規模、財力によって限界があります。
そして、外発的動機付けに偏った考えを組織内に植え付けてしまうと、給与を上げ続けた先、企業の賃金制度上支払える限界に達したときに危機が訪れます。本人が外発的動機付けを習慣化していた場合には、「もっと給料がほしい」「なぜ、上がらないのか」「俺は評価されていないのか」などと、状況によっては積極的転職の後押しをしたり、社員の不満を醸成したりする機会をつくることにもなります。
他方の内発的動機付けとは、内面から湧き起こる、個人の興味や関心、そこから生まれるやりがいなどのことで、企業側が設定するものではありません。つまり個人に起因するがゆえに、自己コントロールすることも可能なものです。
例えば、ラーメン好きな人が、「全国の有名ラーメン店の食べ歩きを楽しんでいる行為」は、内発的動機付けにもとづいています。
逆に「仕事でレシピ開発を担当することになり、よいレシピの開発が、来年の昇格に影響するため、競合店の市場調査をする行為」は、逆に外発的動機付けにもとづいているというわけです。どちらも重要な「やる気」を引き起こす動機付けには違いありません。どちらかに優劣があるわけではなく、大切なのはバランスです。
報酬だけで、やる気をあげようとすると陥りやすい危機
あらためて、外発的動機付けの場合を考えていきます。そこで得られる報酬そのもの(外的に設定されたこと)が目的となるため、「〇〇が得られるなら□□」と、どうしてもトレードオフの心理状態に陥りがちです。
内発的動機付けのほうは、自分の行動そのもの(自身の将来の成功や成長につながること)が目的なので、仕事の成果を出そうと、必要とされる以上のことに、主体的に取り組んでいく可能性が高くなります。
ただ、実際に企業現場で話を聞くと、「やる気に働きかける要因」を外発的動機付けに頼りすぎている企業が圧倒的多数派です。
なぜでしょう?
1つには、外発的動機付けはシステムや制度として一定期間で一斉に、展開することができるからです。そして、もう1つの理由としては、過度の労力やソーシャル・モーメントスキル(本来、人と人が仕事をする上で欠かせない接点を思考しながら取り組むスキル)を必要としないからだといえます。
要するに、一見ラクなのです。しかし、実際には次のような面倒事を抱え込む可能性があります。
- やる気を創出し続けるため、常に目新しいシステムや制度に組み替える必要がある
- 多くの社員が「企業がなんとかしてくれる」という思考から抜け出せなくなる
- 自らの信念にもとづいた目標の設定、将来展望が描けなくなる
- 仕組みや制度で人の満足は高まらないと分かっているが、方針転換できなくなる
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
ITmedia エグゼクティブのご案内
「ITmedia エグゼクティブは、上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした無料の会員制サービスを中心に、経営者やリーダー層向けにさまざまな情報を発信しています。
入会いただくとメールマガジンの購読、経営に役立つ旬なテーマで開催しているセミナー、勉強会にも参加いただけます。
ぜひこの機会にお申し込みください。
入会希望の方は必要事項を記入の上申請ください。審査の上登録させていただきます。
【入会条件】上場企業および上場相当企業の課長職以上
アクセストップ10
- 「頑張りすぎるリーダー」ほどチームを停滞させる? 「自己犠牲」が主体性を奪うメカニズムとは
- なぜコーポレートITはコスト削減率が低いのか――既存産業を再定義することでDXを推進
- 絵画の傾きを皆で調整するな! 鳥瞰力で推進するリーダー - 村田製作所 楠本氏
- 定年後の給料が4割減……40・50代が知らないと地獄を見る“再雇用の残酷すぎる現実”
- 第47回:孫正義氏から怒られて気がついた、経営幹部が果たすべき本当の役割とは
- 日本の現場人材、2040年に260万人不足の試算 フィジカルAIで代替できるか
- これも詐欺? セキュリティ導入時に起きる悲劇をなくせ──「登録セキスペ」で地方・中小企業を救うIPA
- 万博施設を遠隔で解体、無人重機の活躍を未体験記者がリポート 閉幕から4カ月
- 五輪ゴールラインで1秒間に4万枚の画像撮影 公式記録を担う時計のオメガ、タイム計測も
- トヨタと日産が1月の中国新車販売プラス 日産はファーウェイ技術採用のガソリン車が好調
アドバイザリーボード
早稲田大学商学学術院教授
根来龍之
早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授
小尾敏夫
株式会社CEAFOM 代表取締役社長
郡山史郎
株式会社プロシード 代表取締役
西野弘
明治学院大学 経済学部准教授